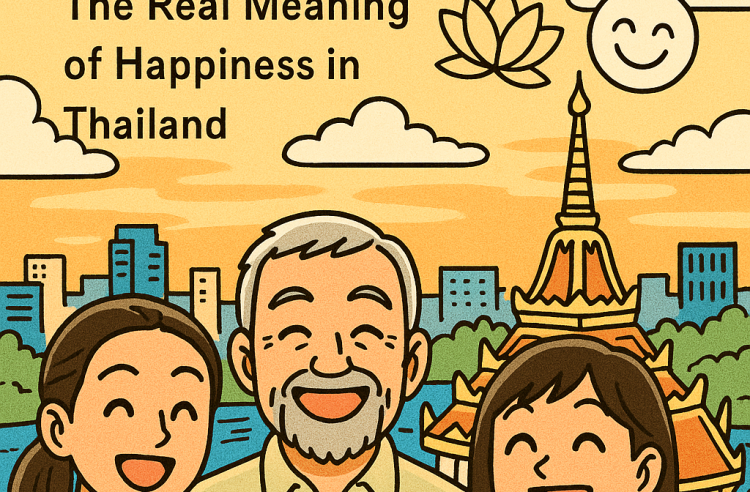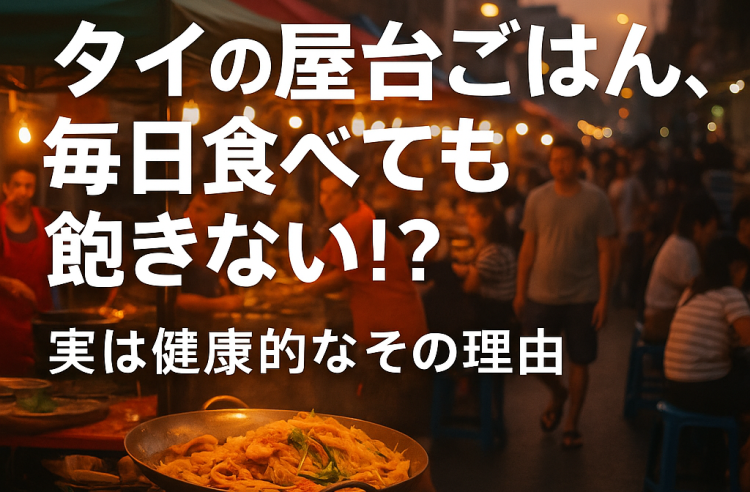タイの人間関係って独特?
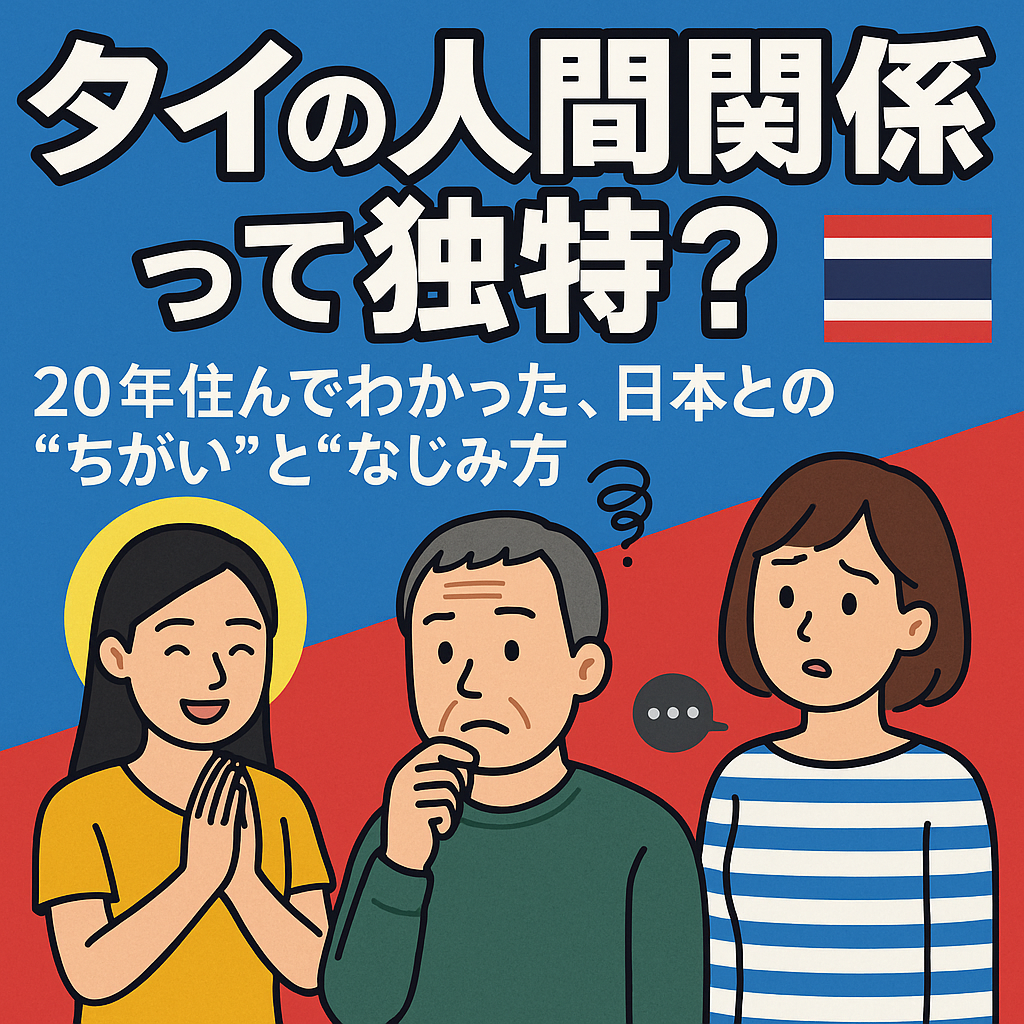
タイの人間関係って独特?──20年住んでわかった、日本との“ちがい”と“なじみ方”
「タイの人って、やさしいよね〜」
「でも、なに考えてるのか分かりにくいときもあるよね…」
これは、日本から遊びに来た友人がポロッとこぼした一言。
実は僕も、タイに移住したばかりの頃は、**タイ人との人間関係の“距離感”**に戸惑いっぱなしでした。
気づけばタイでの生活も20年。今ではすっかり慣れたつもりですが、それでも時々「やっぱり違うなぁ」と感じることがあります。
今回は、タイと日本の人間関係の違いについて、僕自身の体験を交えながらお話ししたいと思います。
タイの人間関係って「近い」の?「遠い」の?
タイ人はフレンドリーで明るい――これはよく言われることですが、実際に暮らしてみると、それだけでは語りきれない「不思議な距離感」があります。
たとえば、
- 初対面でもニコニコ話しかけてくれる
- 近所の人とすぐ打ち解けられる
- お店や役所でも、冗談を交えた会話になる
このあたりは、日本人にとってはとても“ウェルカム”に感じます。
でもその一方で、ある程度親しくなったと思っていた人が、急にそっけなくなったり、連絡が取れなくなったりすることもある。
そう、タイの人間関係は「入り口は広いけど、奥まではすぐには踏み込めない」。
どこか“ふわっと”していて、つかみどころがない感じがするんです。
「マイペンライ」と「遠慮しない優しさ」
タイ人との関係を語る上で欠かせないのが、「マイペンライ(ไม่เป็นไร)」という言葉。
日本語で言うと「気にしないで」「大丈夫だよ」的な意味ですが、これは人間関係の中でも頻繁に使われる魔法のような言葉です。
例えば――
- 電話をかける時間が少し遅れても「マイペンライ」
- 約束に5分10分遅れても「マイペンライ」
- 忘れ物をしても「マイペンライ」
これが、日本人の感覚で「時間厳守・礼儀第一」で育ってきた僕には、最初はかなりのカルチャーショックでした。
でも、その背景には「相手を責めない」「おおらかに接する」というやさしさの文化があると気づいたとき、少しずつタイの人間関係が心地よくなってきた気がします。
「断らない」けど「答えない」こともある?
タイ人の特徴として、「はっきり断らない」「NOを言わない」こともよく挙げられます。
これは、相手の気持ちを傷つけないための配慮でもありますが、ビジネスや実務では困る場面も…。
たとえば、
- 「これ、できますか?」と聞くと「ダイカップ!(できます)」と言う
- でも翌日には「やっぱり無理でした」…
- 理由を聞いても「ちょっと問題があって…」で終わってしまう
これは、日本的な「責任感」や「正確さ」を期待すると、ストレスになる部分です。
でも逆に言えば、「その場の空気を大事にする」「衝突を避ける」文化があるとも言えます。
「家族的なつながり」が強いタイ社会
もう一つ、日本と大きく違うと感じるのが、**「血縁・地縁の強さ」**です。
- いとこ同士でも、まるで兄弟のように仲が良い
- 母方・父方どちらの親戚とも頻繁に交流する
- 親の面倒を見るのは当たり前、という価値観が強い
これは、都会の若者でもあまり変わっていません。
つまり、タイ人の「人との距離感」は、家族や地元に根ざしたものがベースになっているという印象を受けます。
だからこそ、外国人である僕たちがそこに入り込むには「信頼されるまで、時間がかかる」こともある。
でも一度仲良くなれば、ものすごく深く付き合えるのも、タイ人の魅力です。
ご近所づきあいから学んだ「頼ること」の大切さ
僕が住んでいるのは、ローカルな住宅地。コンドミニアムではなく、一軒家です。
近所の人とは、ちょっとした声かけをきっかけに、ゆるやかな関係ができています。
- 風が強い日は、「物干し飛びそうだよ」と教えてくれる
- 車がパンクしたときには、すぐに男手が集まってくる
- 家で採れたバナナを分けてくれる
最初は「ありがたいけど、ちょっと気を使うな…」と思っていたのですが、今では「助け合う」ことがごく自然になってきました。
日本では「人に迷惑をかけないこと」が美徳とされますが、タイでは「迷惑をかけ合うことで人間関係が育つ」面もある気がします。
まとめ:「違う」からこそ、おもしろい
タイと日本の人間関係は、やっぱり違う。
でも、その“違い”に戸惑ったり、笑ったりしながら付き合っていくうちに、「あ、これもアリかも」と思えるようになってきました。
- 距離感がふわっとしているからこそ、心の余裕がある
- マイペンライ精神が、救いになることもある
- 助け合いの中に、人のぬくもりがある
20年暮らしても、いまだに「勉強になるなあ」と思う瞬間がたくさんあります。
きっと、それがこの国の人間関係の“奥深さ”なのかもしれません。